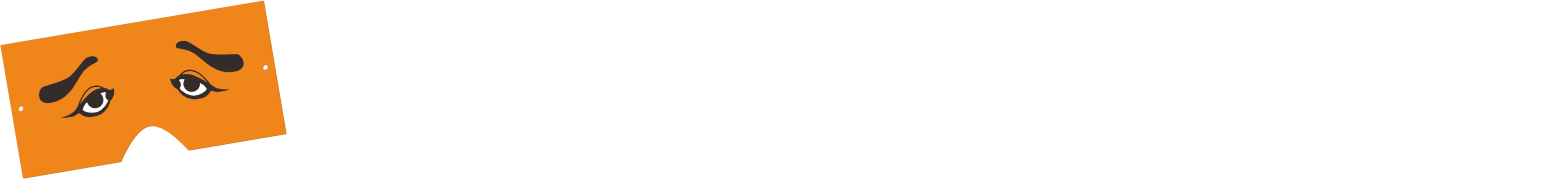福岡News
- 福岡News1
- 博多にわか ― 笑いに込めた人情と風土の芸
- 福岡News2
- 小倉織 ― 縞が語る、まちの記憶と誇り
- 福岡News3
- 福岡アルバム
- 福岡News4
- 大会期間中に北九州で開催されているイベントを御紹介
博多にわか ― 笑いに込めた人情と風土の芸

博多のまちには、誰かを笑わせることで、そっと心に寄り添う文化があります。その象徴ともいえるのが「博多にわか」です。
「にわか」とは、即興の芝居や掛け合いのこと。特に博多においては、半面のお面を付けてユーモアたっぷりの寸劇を演じる伝統芸能として親しまれてきました。現代の漫才やコントに通じるような軽妙な掛け合いが特徴ですが、その根底には、博多っ子ならではの人情味と、ちょっと皮肉のきいた優しさが流れています。
にわかの起源は庶民の笑い
博多にわかのルーツは江戸時代後期にさかのぼります。当時の町人たちが、祭りや寄合の席で即興の笑いを披露し合ったのがはじまりとされ、専門の役者ではなく、魚屋や大工といった普通の町人たちが主役でした。
言ってしまえば、にわかは「素人の芸」。けれど、だからこそ生活の中に根づいた笑いであり、気取らず、わざとらしくなく、聞く人の肩の力を抜いてくれる温かさがありました。
博多の風土が育んだ芸
博多の町は港町として栄え、古くからさまざまな文化が交差してきました。そんな開放的な気質と、お祭り好きの風土が「にわか」の土壌となっています。毎年7月に行われる博多祇園山笠でも、にわかは欠かせない存在。山笠の興奮冷めやらぬ夜に、人々が肩を並べて笑い合う――そんな光景が今も残っています。
「つっこみ」に宿るやさしさ
博多にわかの特徴のひとつが、言葉のつっこみで笑いを生み出す構成です。しかしそのつっこみは、相手を傷つけるためではなく、「そげん言うたらいかんばい!」という、博多弁特有のあたたかみがあるのです。冗談の中にこそ、相手を思いやる気持ちがあり、それがにわかの真骨頂と言えるでしょう。
今に生きる博多にわか
現代では「博多にわか芸人」やにわか大会なども開かれ、世代を超えてその伝統が受け継がれています。SNSや動画配信といった新しい媒体を通して、博多にわかの精神は形を変えながら広がりを見せています。
にわかはただの古い芸ではありません。日々の暮らしの中で、ちょっと疲れた心をくすぐり、人と人の距離をふっと近づけてくれる、そんな「笑いの民芸」なのです。
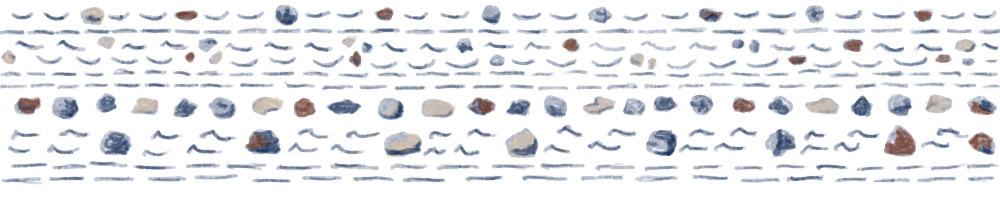
小倉織 ― 縞が語る、まちの記憶と誇り

ホームページのデザインには、「小倉織(こくらおり)」という織物の表情を取り入れています。
それは単なる装飾ではなく、北九州市・小倉のまちが紡いできた歴史や、職人たちの想い、そして地域のアイデンティティを感じてもらうための、静かなメッセージです。
小倉織とは?
小倉織は、福岡県北九州市小倉で江戸時代初期から織られてきた、縞模様を基調とする綿織物です。
なかでも特徴的なのが、経糸(たていと)を極めて高密度に使い、しっかりとした手触りと深みのある色彩を生み出すその技法。繰り返す縞のリズムには、無駄がなく、それでいて強い存在感があります。
かつては「小倉の木綿」と呼ばれ、武士の袴や帯に用いられていました。
その堅牢さと品格が重宝され、「丈夫で粋な織物」として、全国に名を馳せたのです。
消えた織物、そして再生へ
ところが明治以降の時代の変化とともに、小倉織は次第に姿を消していきました。
産業構造の変化、大量生産の時代、戦争、そして技術の継承が断絶しかけたことが、その背景にあります。
しかし1984年、一人の染織家・**築城則子(ついき のりこ)**さんが、わずかに残された資料と布片から小倉織を蘇らせました。
長い沈黙を破って、ふたたびこの地に「縞」が戻ってきたのです。
この再生の物語こそが、小倉という土地の持つ粘り強さ、諦めずに受け継いでいく力そのものだと、私たちは感じています。
地域のアイデンティティとしての「縞」
いま、小倉織は単なる伝統工芸を超えて、まちの文化や精神性を象徴する存在になっています。
学校の制服や市の記念品、企業ロゴに至るまで、小倉織の縞模様はさまざまな場所で息づいています。
整然としながらもどこか自由さを含んだ縞。繰り返しの中にある個性。
それはどこか、小倉のまちそのものに重なります。
小倉織を、いまここに
私たちはこのホームページに、小倉織の精神をほんの少しだけ織り込んでいます。
それは、華美ではなく、でも確かに力のある美しさ。
そして、まちと人が重ねてきた「時間」を可視化する、ひとつの方法でもあります。
どうぞ、スクロールするそのひとときに、小倉の風景や、人々の手仕事に思いを馳せてみてください。
縞の向こうに、まちの物語が見えてくるかもしれません。
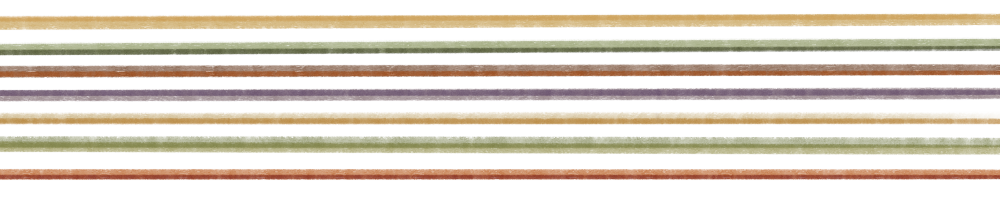
福岡アルバム
運営委員会厳選の福岡の名所を写真でご紹介します。

わっしょい百万夏まつり

吉祥寺公園

小倉城

皿倉山からの風景

皿倉山夜景 (1)

皿倉山夜景(2)

若戸大橋ライトアップ

菅生の滝

北九州市立美術館本館

門司港レトロ

門司港駅

夜景観賞クルーズ