
2014年度及び2015年度役員体制及び名誉会長・相談役
【任期】2014年6月20日〜2016年度に開催される第4回定時総会までの間
| 役職 |
氏名 |
所属(支部) ※1、2 |
選出区分 |
代表理事
会長 |
柏木 一惠 |
浅香山病院(大阪府) |
全国 |
業務執行理事
第1副会長 |
宮部 真弥子 |
谷野呉山病院 脳と心の総合健康センター(富山県) |
全国 |
業務執行理事
第2副会長 |
田村 綾子 |
聖学院大学(埼玉県) |
全国 |
業務執行理事
常任理事 |
洗 成子 |
愛誠病院(東京都) |
全国 |
業務執行理事
常任理事 |
池谷 進 |
健康科学大学(山梨県) |
全国 |
業務執行理事
常任理事 |
岩尾 貴 |
石川県庁(石川県) |
全国 |
業務執行理事
常任理事 |
中川 浩二 |
和歌山県精神保健福祉センター(和歌山県) |
全国 |
業務執行理事
常任理事 |
水野 拓二 |
鷹岡病院(静岡県) |
全国 |
業務執行理事
常任理事 |
渡辺由美子 |
南八幡メンタルサポートセンター(千葉県) |
全国 |
業務執行理事
常務理事 |
木太 直人 |
日本精神保健福祉士協会(東京都) |
学識等 |
| 理事 |
廣江 仁 |
障がい福祉サービス事業所あんず・あぷりこ、はばたき(鳥取県) |
全国 |
| 理事 |
鈴木 浩子 |
相談支援事業所とまっぷ(北海道) |
北海道ブロック |
| 理事 |
長谷川 治 |
青森市保健所(青森県) |
東北ブロック |
| 理事 |
長坂 勝利 |
相談支援事業所ゆりのき(群馬県) |
関東・甲信越ブロック |
| 理事 |
宮村 厚多 |
順天堂越谷病院(埼玉県) |
関東・甲信越ブロック |
| 理事 |
栗原 活雄 |
陽和病院(東京都) |
関東・甲信越ブロック |
| 理事 |
萬山 直子 |
相模原市青少年相談センター(神奈川県) |
関東・甲信越ブロック |
| 理事 |
市村 寧 |
千曲荘病院(長野県) |
関東・甲信越ブロック |
| 理事 |
菅原小夜子 |
こころ(静岡県) |
東海・北陸ブロック |
| 理事 |
鈴木 宏 |
地域活動支援センターめだか工房(愛知県) |
東海・北陸ブロック |
| 理事 |
西川 健一 |
働き暮らし応援センターはっち(滋賀県) |
近畿ブロック |
| 理事 |
知名 純子 |
まるいクリニック(京都府) |
近畿ブロック |
| 理事 |
的場 律子 |
福永病院(山口県) |
中国ブロック |
| 理事 |
小谷 尚子 |
徳島県立中央病院(徳島県) |
四国ブロック |
| 理事 |
今村 浩司 |
西南女学院大学(福岡県) |
九州・沖縄ブロック |
| 理事 |
笹木 徳人 |
グループホームあらかき(沖縄県) |
九州・沖縄ブロック |
理事
(外部理事) |
今福 章二 |
法務省保護局(非構成員) |
学識等 |
| 理事 |
小関 清之 |
秋野病院(山形県) |
学識等 |
| 理事 |
古屋 龍太 |
日本社会事業大学大学院(東京都) |
学識等 |
| 理事 |
松本すみ子 |
東京国際大学(埼玉県) |
学識等 |
財務担当監事
(外部監事) |
梅林 邦彦 |
日本橋事務所・公認会計士(非構成員) |
理事会 |
| 業務担当監事 |
西澤 利朗 |
目白大学(東京都) |
理事会 |
| 名誉会長 |
柏木 昭 |
聖学院大学総合研究所(埼玉県) |
|
| 相談役 |
荒田 寛 |
龍谷大学(滋賀県) |
|
| 相談役 |
大野 和男 |
ぴあ三浦(神奈川県) |
|
| 相談役 |
門屋 充郎 |
十勝障がい者総合相談支援センター(北海道) |
|
| 相談役 |
竹中 秀彦 |
京ヶ峰岡田病院(愛知県) |
|
(理事30名、監事2名、名誉会長1名、相談役4名)
※1 所属の法人又は法人格は省略しています。
※2 2014年8月1日現在
▲上へもどる
役員(正・副会長、常務理事、常任理事、理事、監事)の紹介
- 所属(都道府県)
- 担当の部・委員会等
- 担当の主な関係機関・団体
- 協会活動への抱負
- 構成員へのメッセージ
- 自己紹介
 柏木 一惠(代表理事・会長/全国選出)
柏木 一惠(代表理事・会長/全国選出)
- 浅香山病院(大阪府)
- 高齢精神障害者支援検討委員会助言者、第14回日本精神保健福祉士学会学会長
- 社会福祉専門職団体協議会(社専協)代表者会議構成員、ソーシャルケアサービス従事者研究協議会全体会議
- 会長としての個人的な目標はとにかくバトンを渡す人を見つけることです。協会としては精神保健福祉法改正を受けて宿願の社会的入院の解消、地域生活支援体制の充実に寄与していくことを目指す一方で、新たな精神保健福祉の課題に対応できる人材の育成が必要かと思います。精神保健福祉士の質の担保、社会的課題へのアクションがいつに変わらぬ協会の使命、粛々と進めていきたいと思います。
- 会長になって2年余り、構成員の皆様から様々なご意見、ご提案をいただき協会活動の展開につながったことを改めて感謝申し上げます。
理事も各々の現場を持ち、時間をやり繰りして協会活動をしています。多様な領域から精神保健福祉士に期待されることが多くなった昨今ですが、当然カバーできる領域も限られますし、すべてに応えられる力量があるわけでもありません。多くの皆様が協会活動に積極的に関与していただければと思います。
- 1976(昭和51)年4月に浅香山病院医療福祉相談室に就職し、以後転職はおろか異動もしないまま38年間が過ぎ、2014(平成26)年3月末で定年を迎えました。今は管理職業務から解き放たれ、現場のワーカー業務だけに時間を注げる幸いを感じています。しかし現場は課題だらけ、限られた時間に何ができるか模索の日々です。
ストレスフルな毎日を支えてくれたのは読書ですが、余生は晴耕雨読を夢見ています。
 宮部 真弥子(業務執行理事・第1副会長/全国選出)
宮部 真弥子(業務執行理事・第1副会長/全国選出)
- 谷野呉山病院 脳と心の総合健康センター(富山県)
- 権利擁護委員会、退院促進委員会担当副会長、高齢精神障害者支援検討委員会担当部長、相談支援政策提言委員会担当副会長、組織強化委員会担当副会長、災害支援体制整備委員会担当副会長、診療報酬・配置促進委員会担当副会長、第14回日本精神保健福祉士学会運営委員長
- 今期も、柏木会長を補佐して、副会長をつとめさせていただくことになりました。理事歴も長くなりましたが、当初から、構成員の声を協会活動につなぐことをモットーに活動しています。
公益法人化し、ますます協会が果たすべき役割や求められることが多くなっています。協会が向かうところは何なのか、構成員の皆様にわかりやすく、見えやすい活動をめざして、協会活動に携わっていきたいと思います。
- 精神保健福祉士は、当事者の方々がその人らしく生活していくことを支援する専門職種として国家資格化されました。長期入院の方々の地域移行を推し進め、退院後も安心して暮らすことができ、一方では新たな長期入院を作らないことは、私たちの活動の柱です。精神保健福祉士に期待が高まる中、構成員の皆さんが活躍できるよう側面的にサポートしていくことが協会の使命です。“今こそ、全力支援!!”
- 長年勤めていた民間精神科病院から異動になり、同法人の相談支援事業所にいます。2015年に開通する北陸新幹線の工事進捗状況を横目で見ながら、「やっと乗り換えなしに東京にいける」ことを楽しみに通勤しています。典型的なO型、天秤座、のん気な性格だと思っていましたが、最近「キレる」ことが多くなり、そんな自分にがっかりする毎日です。
最近はまった物は、自家製梅ジュースとサイクロン掃除機。
 田村 綾子(業務執行理事・第2副会長/全国選出)
田村 綾子(業務執行理事・第2副会長/全国選出)
- 聖学院大学(埼玉県)
- 権利擁護委員会担当副会長、機関誌編集委員会担当副会長、「精神保健福祉士業務指針」委員会担当副会長、精神保健福祉士の認証のあり方検討委員会担当副会長、東日本大震災復興支援委員会担当部長、クローバー運営委員会担当副会長、研修センター長、学会誌投稿論文等査読小委員会担当副会長、学会誌投稿論文等査読小委員会担当副会長
- 福祉人材確保重点実施期間推進協議会
- 同じ者がいつまでも同じ役割を負っていると、その人間性に役割が染まったり、イメージが固定してしまったりするように思います。研修センター長として4期目の今期は、後継者への引き継ぎとそのためのシステム整備を第一に考えています。また、協会活動は精神保健福祉士の実践現場の拡大に牽引される形で多岐に広がっていますが、本協会にとっての重要課題の見極めと身の丈にあった活動運営のための判断をしっかり行いたいと思います。
- みなさまの周囲には精神保健福祉士はどのくらいいらっしゃいますか。その中で本協会の構成員は何割ですか。入会せずとも仕事はできますが、よりよい実践を追求し、利用者にとっての重要な資源である自分をよりよく活用するために、本協会構成員であることはどのくらい役に立っていますか。役立っている実感のある方はそれを周囲の非構成員にお伝えください。実感のない方は、まず今年何か一つ協会活動にお越しになってみてください。
- 精神科病院での実習を経て「私が“わたし”らしく居られる場所だ」と感じ、神奈川県の精神科病院でPSWとして社会人をスタートしました。今は大学での教育のかたわら、企業の健康管理センターで社員のメンタルヘルス相談に従事しています。
最近の課題は「断捨離」。この世での欲に包まれた自分をいかに削ぎ落せるか、まだまだ捨てられないものが多くて・・・。中でも難関の一つは“ぜい肉”ですねぇ。
 洗 成子(業務執行理事・常任理事/全国選出)
洗 成子(業務執行理事・常任理事/全国選出)
- 愛誠病院(東京都)
- 機関誌編集委員会担当部長
- -
- 巷では「解釈憲法」なる言葉が歩き始めて、国民の一人としては「なんだそれは?」と危機感を煽られます。選挙の投票率の低さに「もっと関心を持つべきだ」と警鐘を鳴らす文章も目に留まります。社会が良くならないのは市民一人一人の政治への関心の低さに要因があるのでしょう。
翻って、私が協会活動に関わろうと思う動機も「そこ」にあると思っています。考える力も知恵も足りない身ですが、精神保健福祉士として何に関心を持ち続ける必要があるのか学びながら、さらに多くの仲間の関心を喚起することへ微力をつくせればと考えています。
「他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかける。人間のあらゆる失敗は、そういう人たちの間から生まれる。」(A・アドラー)
- 聴の旧漢字は聽。作りの部分は十に四、一、心です。十には調和という意味があるそうです。四は四つの魂、一は霊を意味し、その下に心がある。
つまり、この漢字が何を言っているかというと神道の概念「一霊四魂」ということなのだとか。人間の心を司るものが、人間の心の中で調和している状態。そういう状態で「きく」ことを「聴く」と昔の人は位置付けたのですね。ちなみに一霊は省みる性格(良心)、四魂は勇、親、愛、智を指します。「聴く」ことができる人間を目指す私たちに求められる心のありようはなかなかに深いですね。耳で「聴き」、その心の調和がとれた状態から行動に移したものが「徳」。何事も本質に迫ろうと思ったら簡単ではないけれど、だからこそ面白いのですよね。
- 親しい人たちに言わせる(?)と、一見すると物静か・大人しい雰囲気を装っているのに、しゃべると「毒を吐く」のだそうです(自己認識では装っているわけじゃなく大人しい人間だと思っているので、どうやらそこにギャップがあるんですね)。
シュタイナー流に分析すれば私の気質は典型的なたぷんたぷんの水(粘液)気質でして、外の世界に関心はあるけど反応がスローなんです。周りの人と同じトラックを並んで走っているように見えて、実は周回遅れのランナー!です。でも持久力はあると信じてゴールを目指しております。
自分がスローなので動きのある「風(多血)」や「火(胆汁)」気質の人に惹かれます。
 池谷 進(業務執行理事・常任理事/全国選出)
池谷 進(業務執行理事・常任理事/全国選出)
- 健康科学大学(山梨県)
- 権利擁護委員会担当部長、クローバー運営委員会担当理事
- -
- 一昨年の4月より常任理事として協会活動にかかわらせていただいております。気持ちはつのるのですが、なかなか役割期待に応えられずに四苦八苦しております。本協会も設立50周年の節目を迎え、PSW自らの立ち位置の確立や社会的地位の向上を通したクライエント支援の充実を図ってきたかと思います。国家資格化され、社会からの役割期待や使命は拡がってきております。時機にかなった取り組みを行うことを念頭に置きながら、1期2年間の経験を踏まえ、微力ながらも本協会の充実、発展に資することができるよう努めたいと思います。
- 北は北海道から南は沖縄まで、各地にいらっしゃる構成員のみなさまがPSWとしての共通の価値観に基づいて意見を出し合い、苦しみや悲しみ、喜びなどを共有していく仲間として一緒に協会活動に取り組んでいきましょう!
「日本精神保健福祉士協会に入会していてよかった」と思えるような組織作りのために、みなさまの知恵や力をお貸しください!
- 山口県生まれで山梨県育ち、戌年、魚座、O型です。夏は暑く冬は寒いという盆地特有の厳しい自然があるふるさと山梨が大好きです。山梨県の富士山ネタを全国でまき散らしておりますが、好評、不評さまざまな反応をいただいております。約30年勤めた職場を退職し、富士山の1合目近くに(日本で最標高に)ある大学に通うこととなりました。現場と教育、実践と理論を繋ぐ役割をとれたらと思っております。
 岩尾 貴(業務執行理事・常任理事/全国選出)
岩尾 貴(業務執行理事・常任理事/全国選出)
- 石川県庁(石川県)
- 精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会担当理事、研修企画運営委員会担当理事
- -
- 2008年度に理事になり、4期目となります。これまで、研修事業を中心に協会活動に携わり、昨季から常任理事に就きました。あまり実力があるわけでなく、自分には荷が勝ちすぎていることも多々ありますが、当事者のニーズを大切にし、実践課題をしっかり持って、協会運営に携わっていきたいと考えています。
- 全国大会や研修、委員会活動などを通して、多くのPSWと出会い、自分の成長につながっていると実感しています。
私たちは実践の中で時に迷い、揺れ、悩むことも多いと思います。そんな時に自身を振り返り、精神保健福祉士としての視点や「かかわり」を点検し、自分を磨いていくことが大切だと考えています。今後も皆さんと共に生涯研修制度をよりよいものに育てていきたいと思いますので、ご参加とご協力をよろしくお願いいたします。
- 出身高校の校訓である「自主自律」が好きな言葉です。何事にも主体的かつ自律的に取り組んでいきたいと考えています。
 中川 浩二(業務執行理事/常任理事/全国選出)
中川 浩二(業務執行理事/常任理事/全国選出)
- 和歌山県精神保健福祉センター(和歌山県)
- 退院促進委員会担当部長、組織強化委員会担当部長
- -
- 2期目の常任理事を務めさせていただくこととなりました。今期から組織強化委員会及び退院促進委員会の両委員会の担当部長の任も仰せつかりました。組織強化委員会では、新たな代議員制の体制整備が重点課題となっています。これには皆様のご理解なしには成り立たない事業であります。また退院促進は、私たち精神保健福祉士に課せられた重責課題でもあり、両委員会でお役に立てることを心から感謝しているところです。構成員各位のご支援とご協力をお願いします。
- 最近、偶然でしょうか、あちらこちらで「精神保健福祉士はいるけど、ソーシャルワーカー(PSW)がいなくなった」という言葉を耳にします。先人に呆れられることのないような、PSWスピリッツを持った精神保健福祉士でありましょう。
- 精神障害者に関わる仕事を始め26年目となりました。人生の半分以上が精神障害者との関わりです。これまでも施設や医療機関、保健所等といろいろなことを経験させて頂き、人のつながりに感謝しています。県庁での仕事も7年目となります。職場では地域移行の担当をしていますが、自身が早く事務から現場へと地域移行したい気持ちです。今後も新しいことをめんどうくさがらずに邁進していきたいと思っています。
 水野 拓二(業務執行理事・常任理事/全国選出)
水野 拓二(業務執行理事・常任理事/全国選出)
- 鷹岡病院(静岡県)
- 相談支援政策提言委員会担当部長、診療報酬・配置促進委員会担当理事
- -
- 前期より委員会活動には参画しておりましが、今期、理事経験もない中、新人(常任)理事として協会運営に携わらせていただくことになりました。経験不足ではありますが、一構成員に一番近い執行役員として、現場で起きていることを発信し、協会活動へ活かせるよう取り組んでいきたいと思います。先達PSWの活動を手本とし、微速前進ですが謙虚に協会活動に貢献できればと思います。
- 協会運営には様々な難題が多くありますが、構成員一人ひとりの知恵と力が集約することで乗り越えられる課題だと思います。みなさまに協会活動への協力について突如連絡があるかもしれません。その時はどうか嫌がらずご協力、ご助力お願いいたします。
- 北海道生まれですが青森県でこの業界に入り、現在は静岡県で勤務しています。各県協会活動、本協会の活動に参画することで全国に多くの仲間ができました。縁と義理人情を大切にしています。これからも出会うたくさんの方々との縁も大事にしたいと思います。関係ありませんが、「ワンピース」と「水曜どうでしょう」が好きです。PSWがひとつながりになり、時にはサイコロでも振りながら、新世界の荒波(難題)を越えていきましょう。
 渡辺由美子(業務執行理事・常任理事/全国選出)
渡辺由美子(業務執行理事・常任理事/全国選出)
- 南八幡メンタルサポートセンター(千葉県)
- 災害支援体制整備委員会担当部長、「精神保健福祉士業務指針」委員会担当理事
- 日本発達障害ネットワーク(JDD)代議員
- ブロック選出理事を2期務めさせていただき、今回初めて業務執行理事として協会活動に携わることになりました。公益社団法人となり、さらに代議員制への移行を前に、理事として、また一構成員として、今後の協会のあり方を考えていきたいと考えています。
- 構成員として、協会の活動を通して、今後の施策のあり方や精神保健福祉士としてのあり様を考えることは、とても大事なことだと思っています。日常業務は大変お忙しいと思いますが、協会の活動や研修などに参加し、参画し、ともに考え活動してみましょう。全国に同じ志を持つ知人が増えていくと視野も広がり、仕事も深まります。
- 辰年、かに座、血液型はA型です。生まれも育ちも現在の生活も東京の下町で、一度も外に出ないまま年を重ねてしまいました。仕事も福祉系の大学を出てから、小規模作業所、精神保健研究所のデイケア研究生、授産施設、市役所の窓口、地域活動支援センターとなり、医療機関でのワーカー経験がないという、この年代には珍しい精神保健福祉士です。いろいろと偏っていますが、よろしくお願いいたします。
 木太 直人(業務執行理事・常務理事/学識等)
木太 直人(業務執行理事・常務理事/学識等)
- 日本精神保健福祉士協会(東京都)
- 学術集会抄録掲載原稿査読小員会委員
- 精神保健従事者団体懇談会(精従懇)代表幹事、日本障害者協議会(JD)監事・協議員、社会福祉専門職団体協議会(社専協)代表者会議構成員・ハンセン委員会委員長、ソーシャルケアサービス従事者研究協議会全体会議・政策研究会、医療心理師国家資格制度推進協議会担当役員、高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会、日本弁護士連合会 精神保健PT懇談会構成員、チーム医療推進協議会代表者会議
- 今年度からは常勤役員が1人体制となりましたが、協会活動が停滞したと言われないように、「選択と集中」に心掛けたいと考えています。精神保健福祉士がソーシャルワーカーとしての本分を発揮できる環境を作ることが、精神障害者のウェルビーイングの獲得につながると捉えて、職責を全うできるよう努めていきます。
- この間精神保健福祉士は15倍増えました。精神保健医療福祉の状況を眺めてみると、着実に変化している部分はあるものの、相対的にはあまり変わっていないようにも映ります。本協会が掲げてきた精神障害者の社会的復権という大きなミッションにどれだけの精神保健福祉士がコミットしてきたかが問われます。協会活動を支えるものは、皆さまの思いや想いです。
- 精神保健福祉士が初めて誕生し、本協会の団体名称を変更した1999年に常任理事に就任して以来、足掛け16年目の理事となります。常勤役員としても早5年が経過しました。
かつて、この自己紹介で自分のことを根無し草のようなものと表現したことがありました。今もあまり変わっていませんが、齢50をとうに過ぎ、そろそろ根を張った生き方をしなければと考えだしました(考えただけかもしれません)。認知機能の低下を楽しみながら過ごしたいと思います。
 廣江 仁(理事/全国選出)
廣江 仁(理事/全国選出)
- 障がい福祉サービス事業所あんず・あぷりこ、はばたき(鳥取県)
- 災害支援体制整備委員会委員長
- -
- 今期においては、新たな役員選挙が始まり、さらに新たな代議員制への移行が進められており、協会運営のあり方が大きく変わりつつあり、将来性のある方針がなされるよう尽力したいと思います。
役割としては、災害支援体制整備において、ガイドライン改訂作業を進め、今期のうちに改訂版の発行を目指すと同時に精神保健福祉士に必要な災害支援研修のあり方について検討を続け、研修開催を継続します。
今の自分に課せられた使命は何なのか、それをどの程度果たせているか、自らに問いながら日々の業務を行っていますが、協会運営についても同様に考えていきたいと思います。
- 協会役員に対し、気軽にご意見を言っていただけるような機会を多く作りたいと思います。協会運営について、国への提言について、災害支援についてなど、私も含め構成員一人ひとりが、精神障害者の社会的復権や国民の福利が前進するため、協会のできることについて考えることが大事です。個人で、職場で、支部で話し合った声を執行部にお寄せください。
- 早いもので、病院で8年、作業所で12年、現職で5年とPSW歴が25年を超えてしまいました。協会運営に携わらせていただいた期間も、今期で通算10年を迎えることになります。職場では、法人運営業務のウェートが重くなりつつも、目の前のクライエントとの語らいの重要さを実感しています。協会活動もSW実践も、常に過渡期であるかのような感覚から脱却できず、いったいいつ踊り場がくるのだろうと思いながらガタのきた体で走り続けています。
 鈴木 浩子(理事/北海道ブロック)
鈴木 浩子(理事/北海道ブロック)
- 相談支援事業所とまっぷ(北海道)
- 組織強化委員会委員
- -
- 北海道選出ブロック理事3期目となります。右も左もわからずただ名を連ねるだけの1期目から、2期目は組織強化委員会の一員として末席を汚してきました。力不足は否めず、十分に貢献できたとは言い難い4年間でしたが、3期目となるとそうばかりは言っていられません。改めて職能団体としての協会の充実および発展のために自分が今できる事、すべき事は何かを熟考し精一杯取り組んでいく、そんな2年間にしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
- 協会活動が充実、発展するためには、構成員の皆さんの積極的な参加はもちろんのこと、協会に入会していない精神保健福祉士の方々の参加が不可欠です。周囲に日本協会未加入の精神保健福祉士がいらっしゃいましたら、是非入会を勧めて欲しいものです。それも協会活動の一つです。一人ひとりの力は小さくても結束したときの力は計り知れません。協会入会や活動参加はソーシャルアクションの一環に他なりません。
- この仕事を始めてからかなりの時間が経ちました。そのほとんどを精神科単科の病院で過ごしました。その間、旧法の社会復帰施設に施設長として3年間席を置きましたが、地域で生活することを改めて考えさせられた貴重な体験でもありました。現在は、クリニックの一角に併設された相談支援事業で、外来の相談援助業務と平行して相談支援専門員として活動しています。今年の7月に開設したばかりなので、PSWとしてはもみじ(高齢者運転)マークですが、相談支援専門員としては初心者マークを頭の先からつま先まで付けている気分です。
 長谷川 治(理事/東北ブロック)
長谷川 治(理事/東北ブロック)
- 青森市保健所(青森県)
- 組織強化委員会委員、精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会委員
- -
- ソーシャルワーカーとして、クライエントのこれまでの人生の歩みを大切にしてその方を理解しようとすることと、自分自身が持っている資格の歴史を大切にしてそのあり方を考え続けていくことは無関係ではないと思っています。精神保健福祉士としての仕事は、PSWが何十年も培ってきた実践の歴史とつながっているという認識のもと、現場で起きていることから目をそむけず、後進育成に力を入れた協会活動に取り組んでいきたいです。
- 入会動機や日本協会とのかかわり方はいろいろあると思います。私の場合は、当初は非構成員のままで全国大会に時々参加するくらいでしたが、新しい職場ではPSWの居場所を感じられなかったため、入会しました。「昼ご飯を食べるまでPSWでいよう」「夕方までPSWでいれば、必ず1日が終わる」などと思っていた時期に後輩ができ、認定スーパーバイザー養成研修の受講がきっかけとなって、協会活動に携わる機会に巡り合いました。出会いやきっかけは偶然かもしれません。でも、つながりや支え合い、精神保健福祉士でいられる喜びは同じであってほしいと願っています。
- 非福祉系大学に在学中、サークルで福祉施設や病院を訪問しているうちに福祉の現場に興味を持ち、卒業後、社会福祉士の養成施設で初めて社会福祉を学びました。知的障害者(通所・入所)授産施設、精神障害者地域生活支援センターでの勤務を経て、「役所にソーシャルワークを根付かせたい」という若気の至りで大嫌いだった公務員になりました。市役所に入って11年目になりますが、いまだに、毎日スーツを着ている自分の姿を見て、「うそでしょ?」とつぶやきそうになるときがあります。
 長坂 勝利(理事/関東・甲信越ブロック)
長坂 勝利(理事/関東・甲信越ブロック)
- 相談支援事業所ゆりのき(群馬県)
- 組織強化委員会委員、精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会委員
- -
- 県支部活動では災害支援やイベント事での指揮役を担い、多くの仲間を捲込みながら組織の活性化に努めてきました。代議員となり初めて協会活動に関わり、執行部や他支部の状況を見聞きして多くの課題を共有出来ました。及び腰で理事となりましたが、組織強化委員を担うにあたり協会の活性化そして組織力向上に拙い経験を活かして貢献したいです。楽しめないと仕事が嫌いになる性分ですので、活動の中で早く楽しみを見つけていきたいです。
- 今期からブロック理事となりました。元来思考はポジティブなのですが行動面がとてもネガティブです。故に普段は独り○○が多い人間です。けど、仲間に助けられる事も得意です。同じ様な構成員の方も少なくはないと思います。仲間や繋がりの大切さを知ってはいても孤軍奮闘をしている人も多いのでは。活動に携わる迄行かずとも、今より“もう一歩”近づいて協会活動に目を向けて下さい。個人的には、九州・沖縄ブロックの空気感が好きです。
- 民間企業の営業マンから精神保健福祉士へと転身して、3度目のW杯シ―ズンを迎えました。精神科病院のPSWを経て、2013(平成25)年末〜相談支援事業所で四苦八苦しながら念願の地域で奮闘しています。新しい物にはついて行けず、古い物やくたびれ感が好きなアナログ親爺です。奇妙な人に見られますが、ジャイアンツやG馬場を愛する実は王道が好きです。「他人には甘く、自分には更に甘い」と近しい人からはよく言われます。
 宮村 厚多(理事/関東・甲信越ブロック)
宮村 厚多(理事/関東・甲信越ブロック)
- 順天堂越谷病院(埼玉県)
- 退院促進委員会委員
- -
- 私は若輩者で至らない点ばかりです。ですが、自分の中で大切にしていることがあります。それは、相談者の方に、結果はどうであれ、最後に精神保健福祉士の人に「相談して良かった」と思っていただけることです。
それはすなわち、どの精神保健福祉士に相談したとしても、相談をした人が「相談して良かった」と思っていただける。それこそが、精神保健福祉士の価値であると考えております。そのようになれるように協会と構成員の皆様方と共に価値観を共有し、質の向上につながるようしたいと思っています。
- 私は、今年度でようやく精神保健福祉士になってから6年が過ぎようとしています。職場の精神保健福祉士の先輩に習い、そして県協会の先輩方に習い、現在も、「本当の精神保健福祉士(職人)」を目指し、「悩み」「考え」そして「関わる」ことを続けています。そして、これからも続けていきたいと考えています。今回いただけたこの機会で、さらに研鑽し自分自身もベテランの先輩方から習っている、「本当の精神保健福祉士の姿」をきちんと伝えていきたいと考えています。
- 大学を卒業し、現役では国家資格に落ちてしまい、一般の会社に入社をしました。しかし、「精神保健福祉士になる」ことへの夢を諦められず入社した会社を1年足らずにして辞め、再度国家試験を受験し、何とか合格することができました。そんな経歴ですが、「本当の精神保健福祉士(職人)」を目指し、日々研鑽を積んでいます。到底、職人の域に達してはいませんが、みなさまのご指導ご鞭撻をいただければと思います。何卒よろしくお願いいたします。
 栗原 活雄(理事/関東・甲信越ブロック)
栗原 活雄(理事/関東・甲信越ブロック)
- 陽和病院(東京都)
- 「精神保健福祉士業務指針」委員会委員、精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会委員
- -
- これまで、東京地区での精神保健福祉士の活動を通じて、地区協会や日本協会とのつながりが重要であると感じてきました。最近は高齢者や障害者の増加、精神保健福祉ニーズの増大により、精神保健福祉士の職域も広がってきています。今後はなお一層、「精神保健福祉士」としての研鑽や、寄って立つ共通基盤が求められていくのではないかと思っています。
1昨年度よりに本協会の精神保健福祉士業務指針作成に加わり、「精神保健福祉士」としての理念や役割・機能、援助技術などについて検討する機会を得、改めて気付かされることが沢山ありました。微力ですが、これまで本協会が培ってきた価値や理念を踏まえ、引き続き業務指針の検証などに参画し、私たち精神保健福祉士にとって有用な基盤づくりに貢献していきたいと思います。
- 本協会に入会した構成員は、様々な研修や協会活動を通じて人と出会い、研鑽し、これらを自分自身のストレングスに変え、成長してきているのではないかと思います。組織としては、精神科医療、精神保健福祉の領域は常に困難な状況にありますが、これまで何度も、仲間と共に困難な時代を乗り越えてきました。今後も「自分を支え、成長させる協会活動」に、一人でも多くの精神保健福祉士が参画することが望まれます。様々な機会を通じて、精神保健福祉士同士の繋がりや活動が一緒にできることを楽しみにしています。
- 大卒後、成増厚生病院に約28年間勤務。入院、外来、デイケアなど各部署を回り、1995年からデイケアに専従。集団の持つ力、利用者が生き生きとしていく姿に、力を貰っていました。2000年頃から認知症の外来に関与し、2005年から高齢者の外来、入院、在宅支援に従事。2009年に現在の法人の老健施設に転勤し、2012年より同法人の精神科デイケアに勤務しています。PSW協会との関わりは、前職の上司が協会の役員で、入会がシステム化されていたため入職時から入会。地区協会にも参加。1992年に東京PSW協会(当時は支部)が設立され、役員として断続的に関わってきました。
趣味は音楽とスポーツ(テニス)・・体は動きにくくなりましたが、支えになっています。
 萬山 直子(理事/ 関東・甲信越ブロック)
萬山 直子(理事/ 関東・甲信越ブロック)
- 相模原市青少年相談センター(神奈川県)
- 研修企画運営委員会委員
- -
- 理事になる前は、理事になる人は雲の上の人のように思っていました。そして1期目の2年間は「場違いな場所に来てしまった」感がどうしても払拭できずに終わりました。今期は「いてもいいんだ」感が持てるような活動をしていきたいと考えています。それをするための具体的な抱負はまだ語れないのですが、微力ながら与えられた役割をこなしつつ、自分にできる新たな役割を見つけていきたいと思います。2年間、どうぞよろしくお願いいたします。
- 私はもともと積極的とは程遠い性格です。人前で発言したり、文章で自分を表現したりというのがとても苦手で、あえてその機会も避けてきました。なので構成員の皆様の前で華々しく何かをすることはまずないと思っていますが、消極的なりに協会活動に参加しようと考える構成員もいるということをお伝えしていけたらと考えています。今までの生き方と相反することをしているので未熟な点だらけですが、温かく見守っていただけるとありがたいです。
- 現在は公共職業安定所で働いていますが、年度末には契約期間が終了しフリーになる予定です。不安定な雇用が社会問題になっていますが、まさに身をもって体験中です。休日は家庭菜園で野菜を育てています。売るほどはできませんが、自分が食べていくくらいは収穫があるので、失業しても、これで生きていけるかもしれないと考えている今日この頃です。
 市村 寧(理事/関東・甲信越ブロック)
市村 寧(理事/関東・甲信越ブロック)
- 千曲荘病院(長野県)
- 診療報酬・配置促進委員会委員
- -
- 今まで県協会の理事を約10年務めさせて頂き、「そろそろいちPSWに戻って…」と思っていた矢先に今期から更なる大役を仰せつかることになりました。何かを変えようとしたとき、地域発で出来る事もある一方、いち地域だけのアクションでは限界な事もあります。地域のアクションと全国規模のアクションが連動し合い一つの大きな流れとなっていけるような働きが出来たらと思っております。
- 全国のたくさんの皆様と膝を交えて熱く語り合える機会を楽しみにしています。その中で皆様の思いを一つの形としていけるよう理事として誠心誠意努力していきたいと思っております。
- 現在は精神科病院で主に認知症治療病棟を担当しています。社会人になり立ての頃は、高齢者、知的障がい者の福祉施設と渡り歩き、PSWを目指し勉強し直し始めたのが2001年。21世紀の幕開けと同時に精神保健福祉の世界に飛び込んだまさに「新世紀のPSW」…ではありますが、実はしっかり介護保険を納めている年齢です。
 菅原小夜子(理事/東海・北陸ブロック)
菅原小夜子(理事/東海・北陸ブロック)
- こころ(静岡県)
- 相談支援政策提言委員会委員
- -
- 様々な制度政策が転換していく中、現場で実践をし続けている私自身は、自分たちの立ち居地を見失ってしまうのではないか、あるいは、必ずしも社会的要請が精神保健福祉士としての専門性を求めているわけではない現実があることに対する危機感を常に感じています。理事として2期目を迎え、精神保健福祉士がソーシャルワーカーとして本来的な実践を積み上げていくことが出来るよう、協会活動を通して様々なかたちで発信できればと思っています。
- 「人と出会う、つながっていく」ということは、私たちの日々の実践の中でとても大切なことです。さらに、自分自身が人として成長していくためにも他者との交わり抜きには考えられません。協会活動はソーシャルワーカーとして、個人としての成長の機会となることと思います。是非、多くの構成員の方々が様々な形でかかわっていくことを期待します。
- 公立の医療機関でPSWとして21年、5年前よりNPO法人の障害福祉サービス事業所へ移り、障害者総合支援法に翻弄されながらも、逆に制度を利用してやろうと意気込みながら「地域をつくる」ことの楽しさを実感しています。ただ、頑張りすぎるところがあるので、燃え尽きないように自分をセーブできるようになりたいと今更ながら自分を見つめなおしているところです。
 鈴木 宏(理事/東海・北陸ブロック)
鈴木 宏(理事/東海・北陸ブロック)
- 地域活動支援センターめだか工房(愛知県)
- 組織強化委員会委員
- -
- 日本精神保健福祉士協会設立50年という節目の年に、期せずしてブロック選出理事という大役を仰せつかることになりました。私たち精神保健福祉士の醍醐味は、精神障がい者ご本人やそのご家族の生きざまに関わらせていただき、ともに伝え合い、わかりあいながら、その世帯の生活困難や生活課題に、ともに取り組み、成長しあえる関係づくりにあると思います。でも、一人の困難や課題が、同じ病や障がいをお持ちの方100人の問題であったり、1000人の問題や課題であったりもします。私たちPSWが連携し、関係諸団体とも連帯し、こうした私たちの援助課題を解決していくためにも、協会の取り組みは、とても価値のある大切なものであると思います。何ができるかまだ分かりませんが、焦点を絞った目標を見つけ、皆さんとともに取り組み、成長したいと思っています。
- 県協会の活動で学んだことがあります。同じ精神保健福祉士という立ち位置で、チームを組んで協会活動に取り組むという体験は、その後の自分のPSW業務の中でも、研修会に参加しても、仲間のつながりがとても強まります。自分の職場内では苦しくても、同じPSWの仲間とともに研鑽しあうことの大切さを、先輩や同輩、後輩から学びました。
もちろん失敗したときの苦さも、誇りに思えることもいくつも経験します。
私も一時、協会の活動に失望し、自分の限界に直面し、目を背けていた時期もありました。でもPSWというこの仕事を続けていく以上、専門性を試されたり、自分の足りなさを思いしらされました。
ぜひ「俺たちチームだぜ!」って言えるようないろんなチームを作って実践して、みんなで楽しんでゆきましょう。
- 日本福祉大学で、坪上宏先生から精神障がい者福祉を学びました。山ばかり登っていたので、卒業後は精神科病院に看護助手として就職してからは心を入れ替えてまじめに勉強し、1992(平成4)年には医療ソーシャルワーカーになりました。急性期病棟や訪問看護、グループホームの設立に関与してきました。2007(平成19)年からはメンタルクリニックで精神保健福祉士として、また兼務で、2011(平成23)年からはNPO法人でグループホームを立ち上げ、3年になりました。今年8月には2つ目のグループホームを立ち上げ、四苦八苦しながらも、日々実践しているところです。
ストレスが溜まると、今も山に登って花の写真を撮っています。
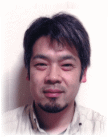 西川 健一(理事/近畿ブロック)
西川 健一(理事/近畿ブロック)
- 働き暮らし応援センターはっち(滋賀県)
- 権利擁護委員会委員
- -
- 理事3期目となりました。精神保健福祉の激動期にこの重責を担うことになり、何ができるのか不安な気持ちでいっぱいです。しかし、協会が何のために存在し、協会の果たせる役割をしっかりと考え、支部の、そしてブロックの仲間のみなさんの声をもとに一生懸命取り組んでいきたいと思います。
- 私たちが最も大切にしている「権利擁護」、どのような実践ができるのか、できているのかみなさんの「声」をどうか届けてください。
先達の築いてくださったPSWの「魂」をしっかりと引継ぎ、制度の枠の中で、職場の枠の中で完結するのではなく、真に必要なソーシャルワーク実践ができるように、ともに迷い、悩みながら一緒に取り組んでいかせてください。
- 聴覚障害を持つ方々とのかかわり、支援から始まり、単科の精神科病院での勤務、そして現在の権利擁護に関わる相談事業を担うNPO法人でソーシャルワーカーとして取り組んできました。
協会活動は2002年から機関誌編集委員に加えていただき、多くの学びを得てきました。そして理事に加えていただき3期目になります。
「わからないことをわからない」「おかしいと思うことをおかしい」と言い続けることのできるソーシャルワーカーであり続けられるよう、ぼちぼちと、でも着実に取り組んでいきたいと思います。
 知名 純子(理事/近畿ブロック)
知名 純子(理事/近畿ブロック)
- まるいクリニック(京都府)
- 組織強化委員会委員
- -
- 理事を務めさせていただくのは2期目です。目まぐるしい前期2年間は、構成員の皆さんからのご意見やアイデアに支えていただきながら過ぎました。今期もみなさんの「クライエントのために」という熱い思いと、この仕事や、組織に対する情熱をしっかり受け止めて、尽力したいと思います。
- 研修を受講して研鑽を積むことや、最新の情報に触れることは大切なことですが、精神保健福祉士として問題意識を持ち寄り、仲間と課題について話し合ったり、活動を展開していく力は職能団体ならではだと感じています。私たちの協会を更に育てていけるよう、どうぞご協力をお願いします。組織強化委員会にも属していますので、みなさんから「協会の一員で良かった」と思っていただける協会にできたらいいなと頑張っております。
- 京都協会では研修部を担当しています。以前は研修への参加人数が会員数に比べても極端に少なかったため、入会したての若い会員やしばらくご無沙汰だった方にも興味を持って足を運んでいただけるような内容を、研修委員の仲間と工夫して企画しています。その甲斐あってか、参加者は以前の3〜4倍になり、ニーズに応える姿勢の重要性とお互いの顔が繋がることの大切さを改めて感じています。プライべートでは茶道を5年習っていて、職場のバンドではBassを担当しています。子どもの頃から切らしたことのないネコ達と今も暮らし、ワインはボルドーが好きなので、どこか引っかかったら気軽にお声かけ下さいね。
 的場 律子(理事/中国ブロック)
的場 律子(理事/中国ブロック)
- 福永病院(山口県)
- 退院促進委員会委員
- -
- 精神保健福祉領域において転換期ともいえる今、私たち精神保健福祉士に求められている“もの”は大きくなり、また多様化しているのを肌で感じています。このような時だからこそ、専門職として何が出来るのか、また何をすべきなのかをしっかりと考えなければならないのでは。資格制度が出来て15年が経とうとしています。日頃行っている業務が“本当にこれでいいのか”、1歩足を止め、振り返り考えるきっかけ作りが提供できるような活動が出来ればと思っています。
- 代議委員・支部代表委員を合わせて6年間務めさせていただき、小さな連携が繋がることで、大きな連携・力を生みだすことを改めて実感しました。そして、その連携から生まれた仲間・力に何度、助けていただいたことか。その力を今度はブロック理事として、皆さんに少しでも返していけたらと思っています。私たちには相談し、また意識を高め合うことのできる専門職仲間が全国各地に沢山います。協会が皆さまの心の拠り所となるような、身近な存在になれば嬉しいです。
- 大学卒業後、精神科病院、精神科クリニックに勤務した後、過疎化の先進地である生まれ故郷に戻り、現在の職場である精神科病院にて働くようになりました。患者さんの殆どが認知症の方ですが、入職の頃と比べ、認知症という疾病が広く知られ、理解が深まるとともに、“相談”の扉が開きやすくなっているように感じています。相談内容も多岐にわたり、悩みや苦悩も増えていますが、院内は勿論、地域の事業所・支援者の方々の協力を仰ぎながら、日々奮闘しています。
 小谷 尚子(理事/四国ブロック)
小谷 尚子(理事/四国ブロック)
- 徳島県立中央病院(徳島県)
- 組織強化委員会委員
- -
- 四国ブロック理事として2期目を迎えましたが、ブロック理事としての責任は重く、今なお理事を務めることの重大さを実感しております。しかしながら、前期の経験と四国の地ならではの現状を踏まえながら、構成員のみなさんと一緒にPSWの心のよりどころとなる組織づくりに向けて取り組んでまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。
- 業務に追われ、PSWとしての立ち位置を見失いそうになるときに、ふと大切なことを振り返させてくれるのがPSW協会とPSWの先輩や仲間の存在でした。迷ったり、悩んだりしたときに、一緒に考え、一緒に悩むことのできるPSW協会の一構成員でありたいと思っています。そのためのPSW協会であり続けられるような活動をしていきたいと思います。
- 精神障害者施設でのPSWをへて、総合病院精神科でPSWをしております。医療提供体制の変化が、PSW業務自体の変化も余儀なくしてしまっていますが、そんな中でも患者さんときちんと向き合いながらかかわっていきたいと思っています。
 今村 浩司(理事/九州・沖縄ブロック)
今村 浩司(理事/九州・沖縄ブロック)
- 西南女学院大学(福岡県)
- 診療報酬・配置促進委員会委員長、クローバー運営委員会委員
- -
- 今期で15年目の理事を仰せつかりました。この間、協会活動で何をやってきたのか、はたまた、何をやろうとしてきたのか・・・・・。九州・沖縄ブロックの精神保健福祉の発展の為・・・・・・・。診療報酬、成年後見・・・・・。いろいろな意味で沢山の課題は山積しておりますが、引き続き、確実にかつ誠実に、さらには丁寧に対応させて頂きたいと思っております。
- 九州・沖縄ブロックでは、沢山の方々のご協力により、各県合同研修会を毎年一回開催という定例化を実現することができました。これからも継続していきたいと思います。また精神保健福祉士の活動のフィールドもかなり広がってきておりますので、さらなる配置促進と適正なる評価を、専門職団体として求めていきたいと思っております。こちらも一歩一歩確実に進んでいければと思います。
- 大学教員ですが、臨床出身で現在も週一日は前勤務先の病院で嘱託職員として活動をさせて頂いています。また、刑務所出所者支援や成年後見活動も行いながら実践を続けています。元来とってもアバウトな男です。悪気は微塵もありませんし、愛想はよいと思います。依頼されたらとっても良い返事ができますが、それを実行することがとても苦手です。今期も引き続き確実、誠実、丁寧に尽力したいと思います。
 笹木 徳人(理事/九州・沖縄ブロック)
笹木 徳人(理事/九州・沖縄ブロック)
- グループホームあらかき(沖縄県)
- 組織強化委員会委員
- -
- 今回、初めてブロック理事として協会活動に携わる事となり、今の自分に何が出来るかは解りませんが、諸先輩方をはじめ、多くの構成員の皆様のお知恵とご経験をお借りして協会活動を務めさせて頂ければと思います。
- 様々な精神保健福祉の分野で改正が行われております。何が正しくて何が正しくないのか不透明な社会となっておりますが、一人でも多くの構成員の皆様の声を拾い上げ、私たちの目の前で暮らしている方々と構成員の皆様の環境が豊かにする事が出来ればと思いますので、よろしくお願いします。
- 精神科病院に勤務して今年で18年目、PSWとしては15年目となります。今年から法人内のグループホームの所属となり、新たなフィールドで仕事をさせて頂いています。協会活動も今年からスタートとなり、色々な意味で心機一転の1年になりそうです。直ぐに調子に乗る一面があるので自制出来る様になる自分に期待したいです。
 今福 章二(理事/外部理事/学識等/非構成員)
今福 章二(理事/外部理事/学識等/非構成員)
- 法務省保護局(東京都)
- -
- -
- 非構成員であり、部外者の立場から理事を仰せつかりました。しかし、当協会への期待は、社会的にも大きいものがあると思いますし、また、今後のことを考えれば、精神保健福祉士としての活躍の場は飛躍的に拡大されてしかるべしと信ずる思いから、できればこのような立場を生かして、協会活動に微力ながら貢献してまいりたいと考えております。
- 精神障害者の人知れぬ悩みに寄り添い、足元の暗闇を優しく照らす灯火たらんと、日々葛藤しながら生き、そして活動しておられる皆様方から、いろいろ学ばせていただければ幸いです。
- 行政の立場から、心神喪失者等医療観察制度の導入・実施に関わったほか、犯罪者や非行少年の再犯を防止しその立ち直りを援助する更生保護の分野で長らく仕事をしてまいりました。最近は、高齢者や障がい者の社会復帰、就労支援、行き場のない人の居場所の確保、そして、覚せい剤等物質依存からの立ち直りなどが、焦眉の課題となっており、精神保健福祉士の活動とも協働すべき場面が増えているものと実感しています。
- 秋野病院(山形県)
- 東日本大震災復興支援委員会助言者
- -
- 一つに、東日本大震災からの復興支援への取り組みに参画させていただいて三年余。二つに、顧みれば在任十年を超える理事の一人として。いずれに於いても、次代を託す仲間と共に未来を構想する手がかりとなる二年間にしたいと思います。
- 一つに、東日本大震災からの復興に向けて懸命に力振り絞る構成員のために、変わらぬ想いと力をお寄せ続けていただきますよう。
二つに、我が国の精神保健福祉を取り巻く冷厳なる現実に臆せず、全国の構成員との紐帯を強め、本協会活動への主体的な参画を担う一人一人でありましょう。
- 学生時代を含む20代を都会で過ごし、30代から生まれ故郷に新設された精神科病院に。50代から地域のネットワークに支えられた診療所にて。そして還暦を過ぎてなおの今、40年余の歴史を刻む精神科病院との出会い。些か老兵なれどクライエントと共にある最前線の一兵卒として、若い仲間に「PSWの魂」のバトンを繋げる日々を歩んでいきたいと思います。
全力疾走すれば蹴躓きダンゴムシ状態に、一発のナイスショットは後ひく筋肉痛を招きます。それでもなお、毎週のテニスだけは欠かしません。
- 日本社会事業大学大学院(東京都)
- 「精神保健福祉士業務指針」委員会助言者
- -
- 歴史は大きく動きつつある。法改正による新たな委員会や相談員の配置、診療報酬の改定などに加え、精神科病床の削減方針と「病床転換型居住系施設」構想が打ち出され、PSWの立ち位置と存在意義が問われている。一人ひとりのPSWが、ただ時流に流されるのではなく、歴史を担い新しく創っていく存在として、自らのミッションを全うできるよう、協会の活動に想いと声と力を結集することを希求し、自らの役割を果たしたいと願う。
- 協会が創立50年の節目を迎える今だからこそ、改めてPSWのミッションと協会の役割を考えよう。与えられた業務をこなすだけになっていないか、制度変革・支援環境開発に向けた取り組みを果たしているか、ソーシャルワーカーとして十分に機能しているか、想いを言葉にして他者と繋がれているか、大切な仲間は疲れていないか、協会の活動が他人ごとになっていないか?粘り強く、静かな戦いを、それぞれの場から発信していこう。
- 1982年より国立精神・神経センター病院でPSWとして勤務しながら、保健所・精神保健福祉センターで相談員を兼務。2008年より日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科准教授、青山学院大学兼任講師。2014年に博士(社会福祉学)学位取得。近著に『Q&Aでわかるこころの病の疑問100』(編著・中央法規)、『ピアスタッフの現在と未来』(編著・批評社)、『精神保健福祉に関する制度とサービス(第2版)』(編著・弘文堂)など。
- 東京国際大学(埼玉県)
- 精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会委員長、学会誌投稿論文等査読小委員会委員
- -
- 言うまでもなく、専門職にとって職能団体の役割は極めて重要です。精神保健福祉士をとりまく社会状況や地域環境は、ますます大きな激流へと姿を変えていますが、こうした社会変動にも柔軟に対応しつつ、しかし本質を決して見失わない確固たる専門性を精神保健福祉士が保持し続けることができるよう協会の活動を充実していくべく、理事としての役割を全うしていきたいと思っております。
- 「つながりあえたらいいなあ!」
いつも思っています。多くの精神保健福祉士が孤軍奮闘している姿を目にするにつけ、精神保健福祉士同志がつながりあう必要性を痛感しています。そして、他の専門職や他機関の人たちや、地域住民とも。「連携」というと何だか急に抽象的になって、その大切さが色あせてしまいますが、いろいろな人たちでつながりあいながら、これからの精神保健福祉をつむいでいけるとよいと思っています。まずは、構成員同士で!
- 精神科医療機関でのPSW実践を経てから現職に就いて、早いもので16年が経とうとしています。精神保健福祉士の養成教育は、日々、真剣勝負です。当たり前ですが一人として同じ学生はいないわけですから、学生ごとに適したやり方を手さぐりで模索し、一人一人と向かい合っていきます。それは教員になり16年経った今でも結構しんどいことです。ただ、慣れや惰性に甘んじた養成教育だけはしたくないと思いながら、日々を格闘しています。
 梅林 邦彦(財務担当監事・外部監事/理事会選出/非構成員)
梅林 邦彦(財務担当監事・外部監事/理事会選出/非構成員)
- 日本橋事務所(東京都)・公認会計士
- -
- -
- 監事の職務であります会計監査及び業務監査を通じて当協会の活動に微力ではありますが、貢献する所存であります。
- 当協会を支えていただいている構成員の皆様とともに、日本の精神保健福祉の増進に寄与したいと思います。
- 私は、現在監査法人日本橋事務所の代表社員として、会社、学校等の監査に従事しております。また、知的障害者関係の社会福祉法人の監事でもあります。
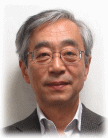 西澤 利朗(業務担当監事/理事会選出)
西澤 利朗(業務担当監事/理事会選出)
- 目白大学(東京都)
- 「精神保健福祉士業務指針」委員会助言者
- -
- 精神保健福祉士の実践が実践分野の広がりとともに大きく拡大しています。実践の拡大は、ともすれば実践の質の低下と拡散につながり、ソーシャルワーク実践の基軸を見えにくくしています。また時代は、他領域で開発された援助方法や技術が無造作に侵入し、効果・効率化、エビデンス主義の強調が、これまで誇りとしてきた「寄り添う人」から「療法士」に代わることを暗に強要します。ワーカーにとって過渡期をむかえているということもでき、ソーシャルワークの復権が強く求められているともいえます。
協会は、組織的強化を求められ、国の政策遂行に振り回される事態に直面されますが、これまでの良き柔軟性と中心軸を常に見失わない姿勢と、協会員の総意を常に奏でる歩みを続けてほしいと思います。
- 私は所属が教員なので、何度も強調する必要があるのですが、精神保健福祉士会は、日々の実践を担っている現場の精神保健福祉士によって、創造される組織でなければなりません。実際、専門性の構築あるいは専門職の養成や試験も含めて、未来に向かう方向性は、現場実践者によって作り出す必要があります。精神保健福祉士の歴史が語るように、研究者・大学人によって主導された時代を繰り返さないでほしい。教員は精神保健福祉士養成の導入部分のほんの一部を担い、かつ現場実践の抽象化や概念化の一部の作業に参与しているにすぎません。精神保健福祉士を育て鍛え、共に歩んでいるのは現場です。
構成員一人ひとりには、内省的実践に基づく専門性の深化と、社会福祉士を含めた全ソーシャルワーカーを牽引する力を発揮することを期待しています。
- 卒業後、川崎市が引き受けた精神障害回復者リハビリテーション施設の勤務からはじまって27年間、川崎で精神障害者福祉の各領域に勤務し、国家資格制定後、私たちの後に続くPSWを育てたいと強く思い、教員となりました。
加齢にともない気力・体力ともに衰え、身体不調も時々出現しています。最近は聴力の衰えがあるのか、認知に弊害が生まれつつあるのか、「千駄ヶ谷」の駅アナウンスが「ダメダガヤ」に聴こえたりします。業務を見つめる監事という役割、重責なのですが自覚少なく、頼りなくもあり、弱っています。何事にもご寛容の程よろしくお願いします。
- 聖学院大学総合研究所(埼玉県)
- 機関誌編集委員会編集代表
- -
- 利用者(クライエント)中心の立ち位置で、発言したいと思っています。したがって、私は「かかわり論」に立って、常に「協働」の姿勢で、利用者を生活者としての視点に置いて、発言、発信していこうと考えています。ここで「協働」とはクライエントの地域生活支援における、様々な思いや希望を受け止め、その解決や実現に向かって「共に吟味、協議すること」と限定して、協会総体として了解しておくように希望します。例えば、保健師や看護師との協力関係は「連携」とします。協働はあくまでも、クライエント(利用者)とのかかわりにおける共同作業です。
- 精神保健福祉法の改正による「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会]のあらましが、柏木会長より、PSW通信No191(2014.7.15)に報告されています。長期入院者ご本人に対する支援の方策とか、病院の構造改革について極めて明快なお考えが述べられています。構成員におかれては、これをじっくり、それこそ行間に込められた会長の思いまで読み取ることができるように、読んだ上、自分の考え方との違いや、賛同できる部分について、深く読み取ることをお願いしたいと思います。
- 自己紹介については、PSW通信No190・191号に掲載しております。たまたまこの時期に名誉会長である私とはどんな人物なのだろうと、お考えになる方もおありだろうかと思ったのが動機です。公器である「PSW通信」という媒体に私的な記事を書いてもいいものか、正直迷いながら、敢えて自己紹介をさせていただいていますので、詳しくはそちらをご参照ください。もともとは大日本帝国海軍士官になり、ゼロ戦を操縦するのが夢であった軍国少年が180度の転回、回心を経てアメリカに留学し、ソーシャルワークを学んだものです。上に記したように、私はPSW通信の毎号に「PSW協会ひすとりい」というコラムに寄稿しています。800字程度の文章ですから、すぐ読めます。往時の協会を振り返るのも意味があると思っています。
★PSW通信連載:「PSW協会ひすとりぃ」(本文閲覧は構成員のみ)
- 龍谷大学(滋賀県)
- 機関誌編集委員会委員、学会誌投稿論文等査読小委員会委員、高齢精神障害者支援検討委員会助言者、精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会助言者
- -
- 精神保健福祉士の資格化までの10年と、資格化後の10年の計20年間、協会の執行部において協会運営に関与してきました。現在は相談役として協会活動に関わっていますが、特に機関誌編集や認定スーパーバイザー養成研修の企画運営を中心に参画してきました。今後も、この二つの活動を中心にしつつ、滋賀県の精神保健福祉士の活動と関西のPSWのスーパービジョンを実践していきます。
- これからも日本精神保健福祉士協会の50年の歴史の中で培われてきた(1)自己決定の尊重の原理、(2)人と状況の全体性の視点、(3)生活者支援の視点、(4)ソーシャルワークの原点である「かかわり」を重視することを専門性の中核として、社会状況や精神保健福祉現場に無批判に「適応」することなく、新しい状況を改革する姿勢を堅持していくことが求められていると思います。
- 日本精神保健福祉士協会の活動に参加して37年になります。協会活動の経験を通して学んだことと、精神保健福祉士の国家資格化の活動が、自分自身の人生でありました。ソーシャルワーカーであり続けることに拘ってきましたが、養成する側になっても、そのことを大切にしていきたいと思っています。また、現在では現場で働く精神保健福祉士の支援も重要な仕事であると思っています。
- ぴあ三浦(神奈川県)
- -
- -
- 精神保健福祉士法の実現は、私が理事長(当時)時代にとり組んだ最大の課題でした。専門職自立の制度的要としてこの精神保健福祉士法がさらに国民の付託に応えられるよう我々の力で磨き上げていく必要があります。
時代状況の変化に翻弄されず、権力に屈せず、我々の専門的・社会的活動が堂々と遂行することのできる専門職として完成度を高めていくことに関心を持ちながらかかわっていくつもりでいます。
- Y問題の継承性の取り組み、「提案委員会報告」と「札幌宣言」、専門性を進化させるための「三点課題」の取り組み、「PSW業務指針」の策定、そして、資格制度実現にあたっての「基本5点」に至る経過は、協会員が一体となった取り組みであり、専門職アイデンティティを形成するうえで重要な位置を占めています。これをあらためて自覚し、今日の自らの実践の糧とするよう研鑽を積むことは大事です。本協会の相談役としてこの立場から役に立つことができればと思っています。
- 本協会50年の歴史の中にあって、私は、45年以上にわたり、一構成員として、また、あるときは、理事や事務局長、あるときは理事長(当時)として組織を運営する立場でかかわってきました。私の社会人としての人生はつねに自分はPSWであることを意識して過ごしてきたように思います。いまは、大学の非常勤教師として精神保健福祉士の養成にあたったり、精神保健福祉領域の市民団体の役員として、利用者や現場のPSWの支援にかかわったり、第三者委員などいくつかの社会的活動にかかわっています。
- 十勝障がい者総合相談支援センター(北海道)
- 相談支援政策提言委員会助言者
- -
- 協会の存在理由は精神障害者の社会的復権を果たすことです。そのための喫緊にやることは全ての入院患者のニード調査です。それぞれのニードを満たす実践です。繰り返される不幸の連鎖を断ち切るための精神科病院の最小化ための運動です。協会は現場で果たせない課題解決を行うために存在しています。社会運動を起こさずして問題解決が図れない課題があるからこそ、余りにも拡散している協会活動を転換させてほしいと願っています。協会活動を整理し、組織総体としての実践課題と行動計画を焦点化させたいものです。
- 私達はソーシャルワーカーです。精神障害者の人知れぬ悩みに寄り添い、彼らから求められる精神保健福祉士であると同時に相談支援専門員(ケアマネジャー)として活動し、彼らを疎外している状況や環境改善を行う実践に期待しています。目の前の矛盾に立ち向かわないならば、専門職としての価値は半減してしまいます。皆さんの実践が彼らの足元の暗闇を優しく照らす灯火となることを祈ります。
- 私は45年間ソーシャルワーカーとして精神科病院、値域で活動し、15年間精神保健福祉士として地域で働き、精神障害者が地域で暮らすをあたりまえに送るための福祉サービス利用の業務独占を持った相談支援専門員として9年間働いてきました。私の最大の関心と課題は精神保健福祉の歴史的転換を図ることです。20万人の入院患者さんの人生を取り戻すことです。それは協会が1982年以来使命としてきた精神障害者の社会的復権を果たす実践をし続けています。
- 京ヶ峰岡田病院(愛知県)
- 精神保健福祉士の認証の在り方検討委員会委員、診療報酬・配置促進委員会助言者
- (公社)日本精神保健福祉連盟理事
- 私は民間の精神科病院でPSWとして39年目、本協会に関わらせていただき20年目になります。この経験をもとに本協会のスムースな運営と充実した協会活動が行われるよう微力ながらお手伝いさせていただきます。
- 協会員であることに誇りを持ってください。
そのために、日常実践では当事者・家族に謙虚に誠意をもって向き合うこと、本協会の研修などに参加する等研鑽に努力します。
- 私は民間精神科病院で39年目になりますが、最近、体力・気力が少しづつ減退している自分に気付くことがあります。しかし、これからの精神保健医療福祉の行方を確認する意味でも、今の現場でもう少し頑張ろうと思います。
△前のページへもどる
 柏木 一惠(代表理事・会長/全国選出)
柏木 一惠(代表理事・会長/全国選出) 宮部 真弥子(業務執行理事・第1副会長/全国選出)
宮部 真弥子(業務執行理事・第1副会長/全国選出) 田村 綾子(業務執行理事・第2副会長/全国選出)
田村 綾子(業務執行理事・第2副会長/全国選出) 洗 成子(業務執行理事・常任理事/全国選出)
洗 成子(業務執行理事・常任理事/全国選出) 池谷 進(業務執行理事・常任理事/全国選出)
池谷 進(業務執行理事・常任理事/全国選出) 岩尾 貴(業務執行理事・常任理事/全国選出)
岩尾 貴(業務執行理事・常任理事/全国選出) 中川 浩二(業務執行理事/常任理事/全国選出)
中川 浩二(業務執行理事/常任理事/全国選出) 水野 拓二(業務執行理事・常任理事/全国選出)
水野 拓二(業務執行理事・常任理事/全国選出) 渡辺由美子(業務執行理事・常任理事/全国選出)
渡辺由美子(業務執行理事・常任理事/全国選出) 木太 直人(業務執行理事・常務理事/学識等)
木太 直人(業務執行理事・常務理事/学識等) 廣江 仁(理事/全国選出)
廣江 仁(理事/全国選出) 鈴木 浩子(理事/北海道ブロック)
鈴木 浩子(理事/北海道ブロック) 長谷川 治(理事/東北ブロック)
長谷川 治(理事/東北ブロック) 長坂 勝利(理事/関東・甲信越ブロック)
長坂 勝利(理事/関東・甲信越ブロック) 宮村 厚多(理事/関東・甲信越ブロック)
宮村 厚多(理事/関東・甲信越ブロック) 栗原 活雄(理事/関東・甲信越ブロック)
栗原 活雄(理事/関東・甲信越ブロック) 萬山 直子(理事/ 関東・甲信越ブロック)
萬山 直子(理事/ 関東・甲信越ブロック) 市村 寧(理事/関東・甲信越ブロック)
市村 寧(理事/関東・甲信越ブロック) 菅原小夜子(理事/東海・北陸ブロック)
菅原小夜子(理事/東海・北陸ブロック) 鈴木 宏(理事/東海・北陸ブロック)
鈴木 宏(理事/東海・北陸ブロック)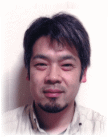 西川 健一(理事/近畿ブロック)
西川 健一(理事/近畿ブロック) 知名 純子(理事/近畿ブロック)
知名 純子(理事/近畿ブロック) 的場 律子(理事/中国ブロック)
的場 律子(理事/中国ブロック) 小谷 尚子(理事/四国ブロック)
小谷 尚子(理事/四国ブロック) 今村 浩司(理事/九州・沖縄ブロック)
今村 浩司(理事/九州・沖縄ブロック) 笹木 徳人(理事/九州・沖縄ブロック)
笹木 徳人(理事/九州・沖縄ブロック) 今福 章二(理事/外部理事/学識等/非構成員)
今福 章二(理事/外部理事/学識等/非構成員) 小関 清之(理事/学識等)
小関 清之(理事/学識等)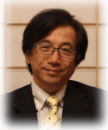 古屋 龍太(理事/学識等)
古屋 龍太(理事/学識等) 松本すみ子(理事/学識等)
松本すみ子(理事/学識等) 梅林 邦彦(財務担当監事・外部監事/理事会選出/非構成員)
梅林 邦彦(財務担当監事・外部監事/理事会選出/非構成員)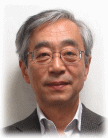 西澤 利朗(業務担当監事/理事会選出)
西澤 利朗(業務担当監事/理事会選出)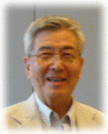 柏木 昭(名誉会長)
柏木 昭(名誉会長) 荒田 寛(相談役)
荒田 寛(相談役)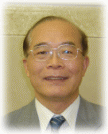 大野 和男(相談役)
大野 和男(相談役)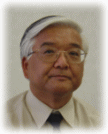 門屋 充郎(相談役)
門屋 充郎(相談役) 竹中 秀彦(相談役)
竹中 秀彦(相談役)